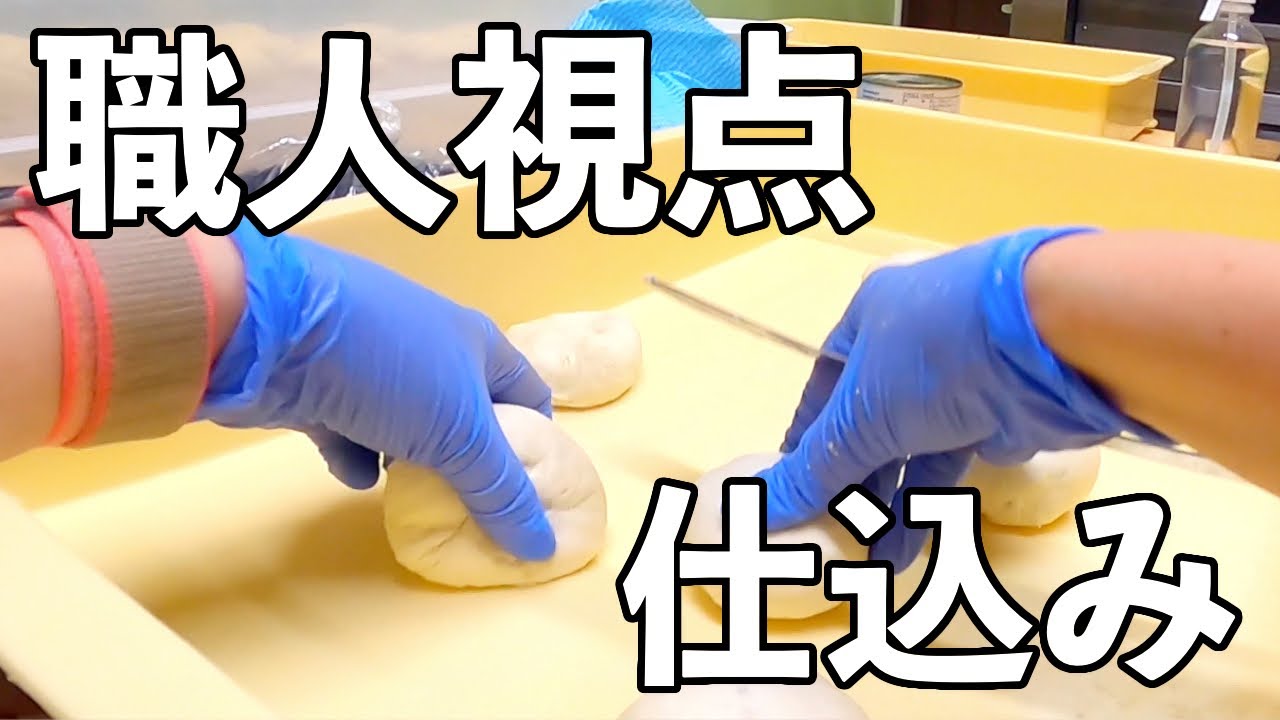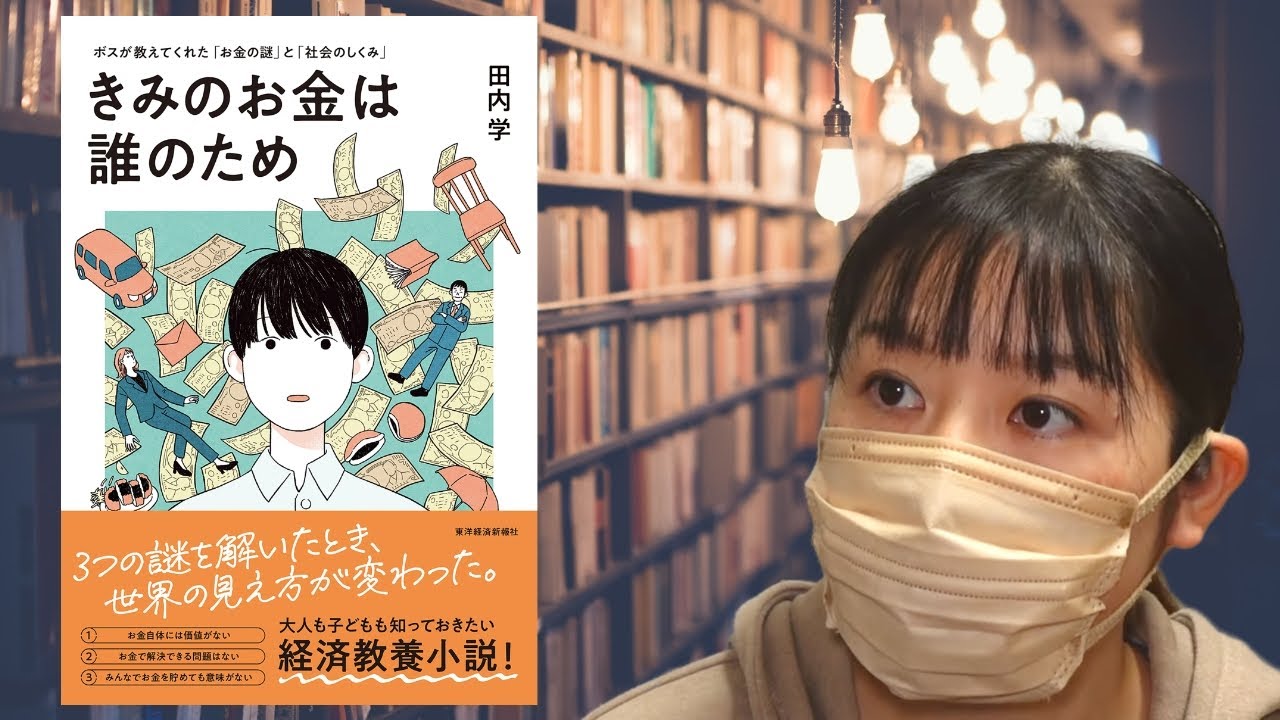見積書の内容について①
お金がないから、必死に予算内でできる限りの工房作りを模索するのは当たり前なのだけど、お金があっても納得できないことには一円でも払いたくないもの。利益あっての商売だけど、あれ?夢みて開業する人をカモにしてふんだくってないかい?と感じてしまった今回の見積書。内容をパートに分けて細かく説明していきます。
見積もり額に、どれだけ盛り込まれているのか?
値切りすぎも違うけど、家に工房を作った友人は、わずか4畳もない部屋で300万かかったと言っていたっけ。棚も言えばササッと予算内で作ってくれてすごくいい大工さんだったよーと言っていたけど、中身を知れば真っ青になっていたのではないか。。
今回のようなサービスの内訳には、物の原価があって、その他諸々上のせしたものが請求金額になります。その中でも一番多くを占めるのがやはり人件費です。
詳しく説明していきます。
職人が、物を仕入れて作業するときに、まず物の値段(原価)があり、そこに発注したりする人の手間賃が乗ります。ここは見積もりをする人によるのですが、だいたい10%〜30%です。
そしてそれとは別に施工の手間賃がかかります。この業界では、人工(にんく)といって、一人あたりの職人さんの日当で計算されます。
これも地域によってはバラバラで、父が現役でやっていた大阪で、父の見積もりでは、1人工あたり25000円〜28000円(この中には父の利益が2000円〜3000円のります)なのですが、今回千葉で見積もられた内容としては、どう計算しても一人工につき50000円とか、60000円、もしくは3人で明らかに作業ができる部分を4〜5人工に見積もりしているのか?と思うしかないような(細かな詳細がわからないのではっきりとはわかりませんが)忙しくてオリンピック前で職人がいないとは言っても、父も驚きの値段でした。
これが、工務店で大工さんを雇っており、その大工さんがやるならまだ安いのかもしれませんが、下請けとして他の会社や大工さんに頼む場合、さらにこの日当に依頼した側の利益が乗ってくるのです。つまり、大工を現場に派遣すれば、何もしなくとも利益が生まれるのです。現場を紹介する力をもつことがどれだけ大きなことなのか。横のつながりが強烈な業界だな、と感じました。
下請けの下請け、とかになってくると、作業量は大したことなくてもマージンがかさんできて、トータルすると日当5万とか、オーナーが最終的に支払うのはそんな数字になってしまうのです。恐ろしいですね。
そしてさらにのるものとして、解体してから施工するなら解体費、復旧費、解体したゴミを処分する産廃費。(ここにも利益のります)さらに雑費、諸経費も侮れないもので、何に当てられてるか不明の明細、諸々急に見積もり以外で必要になってしまったものや、駐車場代なども含まれます。
さらにさらに運搬費といって、物を運ぶ手間賃も請求されます。そこは作業の手間賃としてまとめているところもありますが、、
物も安く仕入れれるのが業者のメリットですが、こんなに大工さんの人件費高いんですか。。とならないように、物の値段を上げたり、それこそ諸経費や雑費に入れ込んでしまうというのもよくあることです。
ここはサービスします、とか、予算内で棚つくります、とか、本当にすご〜くありがたいこともありますが、実は全然違う枠でがっつりその分も取られている可能性もあるということです。