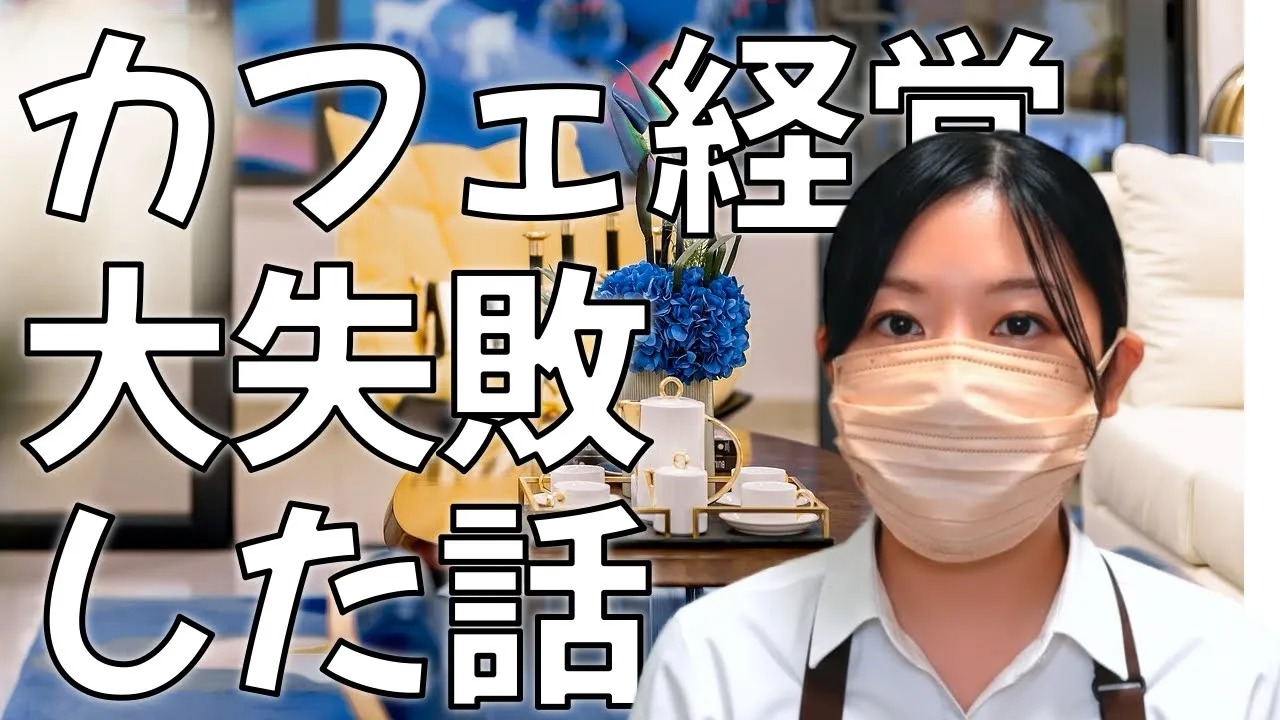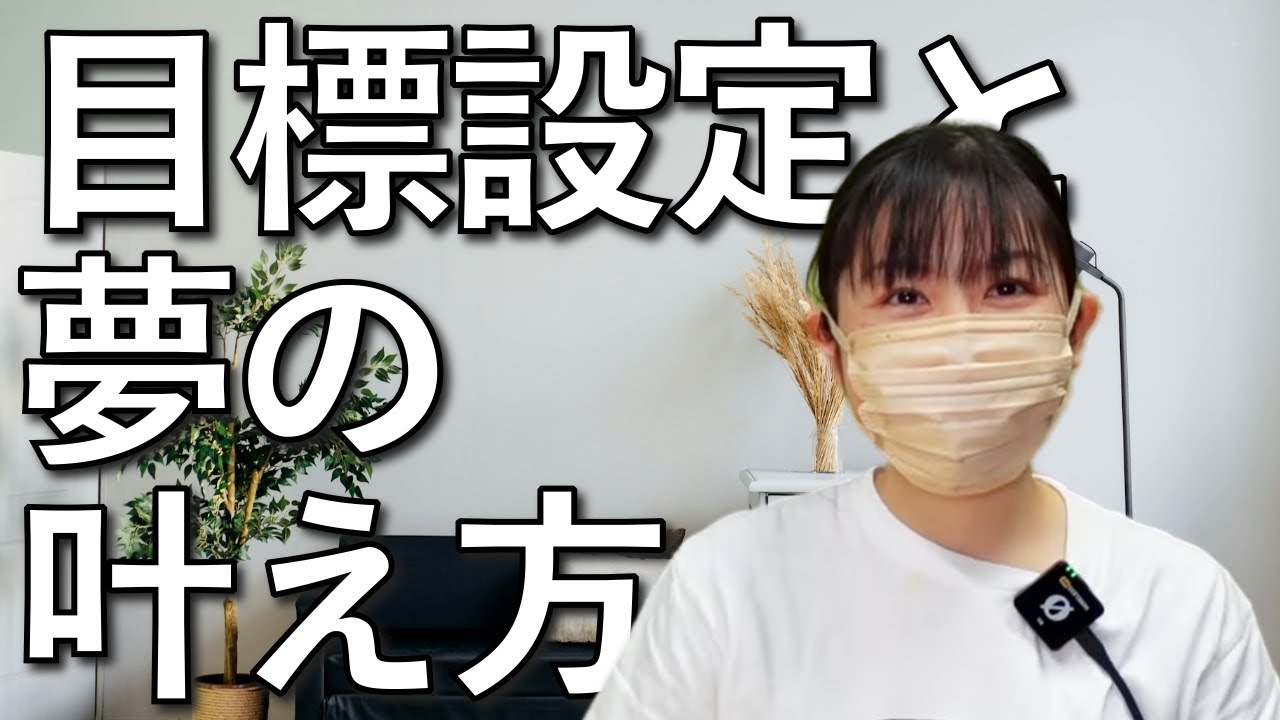日本の食料自給率が落ちた原因を考えてみる
日本の食料自給率が落ちた原因
日本の食料自給率が半分も落ちた原因について考える際、まず私が考えるのは、食べ物が非常に豊かでなく、飢えている時代から人口が増え、食べるものも増えたという仮説です。
食べる量が変わったとか、人口が増えたため日本国内で生産できる食料だけでは需要を満たせなくなったため、自給率が低下したというような考え方があります。
しかし、これはどうやら違うようです。
まず、日本の人口は約55年前には約1億人ほどであり、現在でも約1億2630万人程度であることから、この55年で人口が大幅に(倍ほどに)増加したわけではないことが分かります。
人口が増えすぎたため、自給率が半分に落ちたという理由にはあまり納得がいかないのです。
一方で、食べる量が急激に増えているわけではないことも明らかです。
過去の記録によれば、1965年当時は一人当たり一日にお米を2合以上摂取していたとされています。
この時代は、お肉やおかずがあまり豊富でなく、ご飯が主食であったため、ご飯の摂取量が多かったのは確かですが、今と比較するとそれほど大きな違いはないと考えられます。
次に考えた原因は、日本ではお米の消費量が半分程度に減少し、その代わりにパンや麺の消費が増えたため、輸入小麦に頼らざるを得なくなり、食料自給率が半分に減少したという仮説です。
特にパンの消費が増えていると言われていますが、実際のデータを調べてみると、お米の消費量が半分以下に減少していることが分かります。
しかし、これがパンや麺の消費増加に起因するものではないことも明らかです。
実際に小麦の消費量はほとんど変わっておらず、パン以外にもパスタやラーメン、ピザなど様々な食品がありますが、これらの消費量が急増しているわけではありません。
従って、単純に小麦の消費が増えたから日本の食料自給率が減ったというわけではないようです。
肉が日本の食料自給率を変えた一番の原因!?
ここで、もう一つ大きく変化した食材があることも確認されました。
それがお肉の消費量です。
実際にお肉の年間消費量は驚異的に増加しており、これが食料自給率の大幅な低下の要因の一つである可能性が高いと考えられます。
過去に比べてお肉が豊富に入手可能になったことや、和食から洋食への移行が進んでいることなどが、食料自給率の低下に影響を与えていると言えそうです。
つまり、肉の消費量の増加が食料自給率に影響を与えている一因であることが分かります。
また、とある飲食コンサルティングの人によれば、人が食べられる量はおおよそ決まっており、1食あたり男性は約500〜550グラム、女性は約400〜450グラムが満腹になる量とされています。
この情報から、飲食店はお客様に満腹になってもらうために、料理一つに対するグラム数を計算し、適切な価格設定をすることになります。
これにより、肉が増えたことで食事全体の量が減少したことが示唆されます。具体的には、ご飯の量が減り、肉の量が増えたため、小麦の消費量は増えていないが、肉の割合が増加したことが要因とされています。これにより、肉が占める割合が増加したため、全体の食事量が減少し、食料自給率の低下につながった可能性が高いと説明されています。
つまり、食事構成の変化が食料自給率に影響を与えており、特に肉の消費量の増加がその一因となっていることが示唆されています。
近年、糖質制限ダイエットの流行や糖質ダイエットの影響で、ご飯を減らす傾向があり、同時にお肉は栄養価が高いため本能的に求められ、味でも人気があり、そのためお肉の消費が増加しても不思議ではない。
特に、お肉の美味しさは人が本能的に求めてしまうため、食べたくなる要因にもなっていると考えられます。
また、お肉は栄養価が高いため、消費が増えても驚くべきことではないですね。