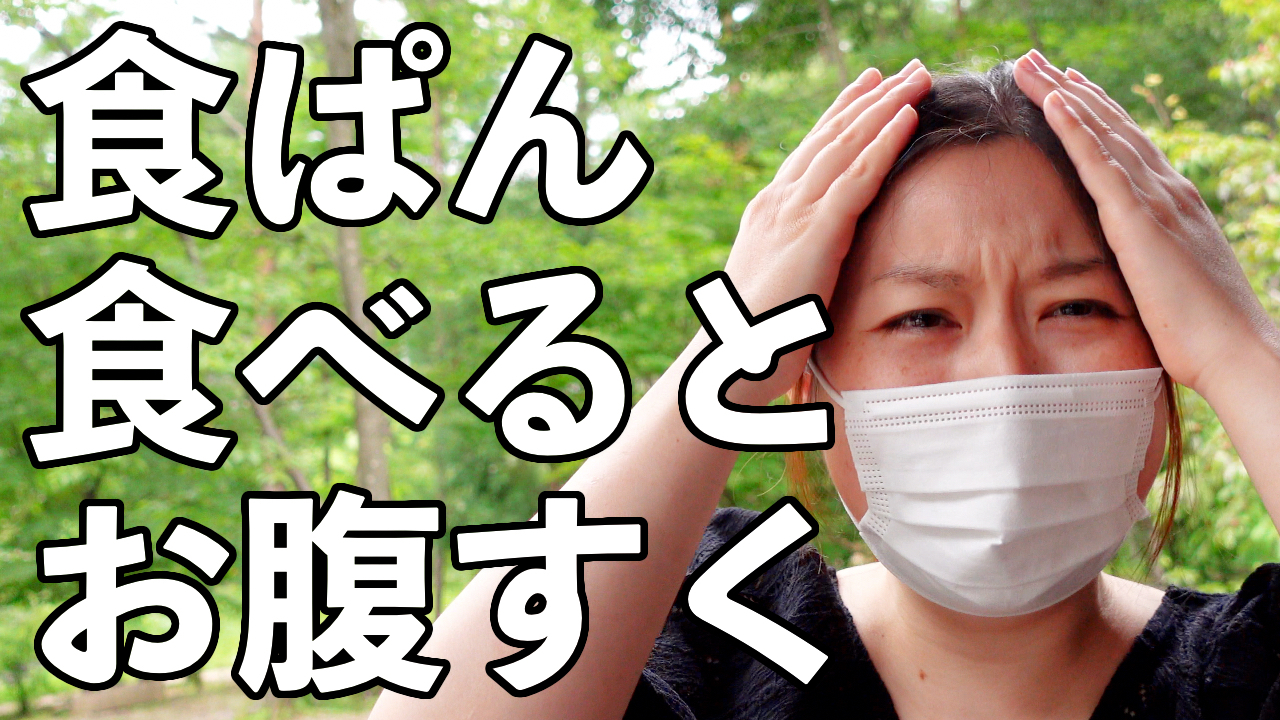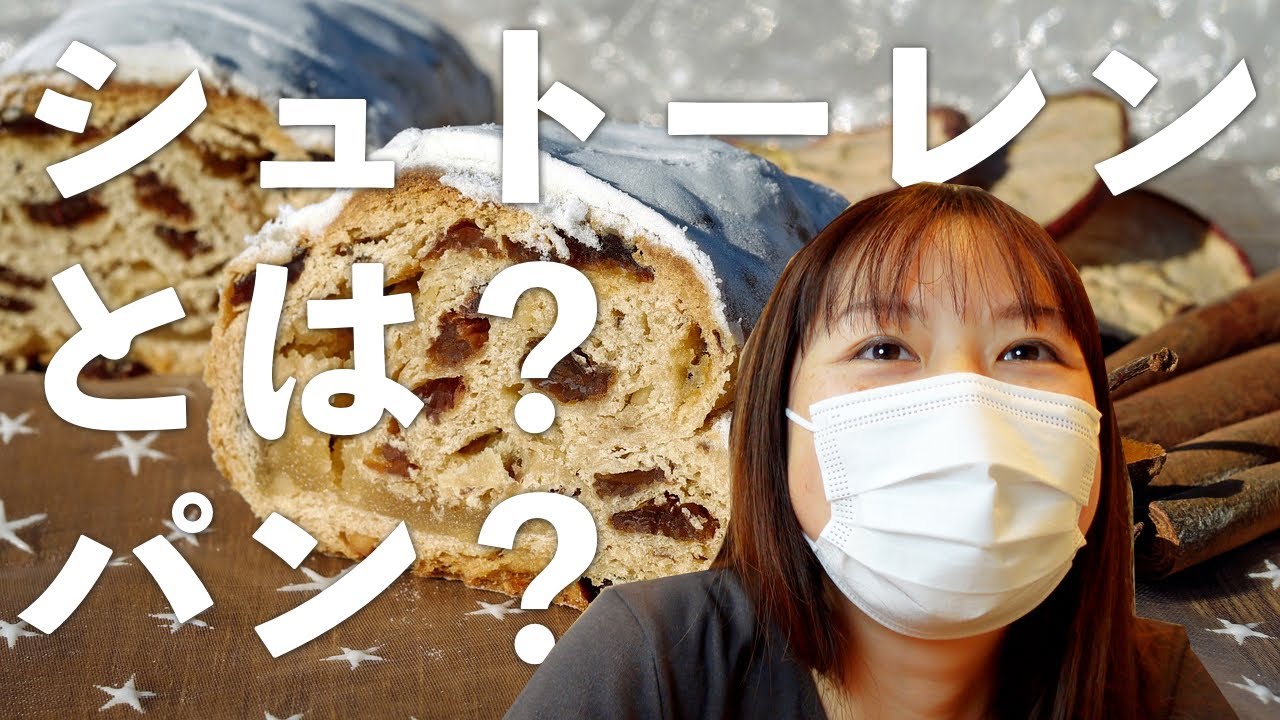国産小麦のパン屋が忖度なしに国産小麦の現状について調べてみた
こんにちわ。ひとぱん工房の店長です。
以前のブログ(以下リンク)外国産小麦については、関心を頂いた方からメッセージもいただけて、書いて良かったです。

今回は前回のブログ続きになります。いよいよ当店(ひとぱん工房)でも拘っております国産小麦について。
国産のパン用小麦ができたのは偶然だった!?
国産小麦の一番の生産量を誇るのは、やっぱり北海道!
日本列島で一番の面積で、ここも土地の広さが生産量の大きな理由になっていると思います。
パンに向いてる小麦粉は強力粉といって、タンパク質とグルテンが一定以上ある小麦になります。
ハルユタカの誕生
日本初のパン用小麦の誕生は1985年(昭和60年)長い年月をかけて開発された「ハルユタカ」です。
「ハルユタカ」は、もともとパン用に作られたものではなく「ハルヒカリ」の代替え品種として麺用に開発されたそうです。
開発の途中にパン作りに向いた品種であることがわかり、製パン用小麦の開発に切り替わりました。
ここから偶然にも国産小麦で作るパンの歴史がスタートしたのです。
これまでの海外から輸入していた小麦とは違う、国産ならではの風味や食感を持つ「ハルユタカ」。
「国産小麦でパンづくりを!」という農家やパン作り手の方々の熱い想いもあり、日本ならではの新しいパンの可能性を提示する小麦となりました。
しかし「ハルユタカ」はその生産の難しさから、後継種の「春よ恋」に今は切り替わっています。
その後も、どんどん新しい品種が生まれています。(以下参照)

ひとぱん工房で使っている国産小麦の品種は?
当店(ひとぱん工房)で使用しているのは、九州地方で生まれたミナミノカオリを100%使用した熊本製粉社オリジナルパッケージ「ミナミノメグミ」です。

ミナミとは、九州の方面を指しているんですね。
ひとぱん工房には全粒粉食べ比べセットという商品があるのですが、熊本製粉「ミナミノカオリ全粒粉」と北海道産「キタノカオリ全粒粉」と千葉県産「ふさの麦全粒粉」で作っています。
全粒粉なので皮の味わい深い濃い味がしっかりして、粉の個性が伝わってきます。
国産小麦の需要も年々高まり、大手メーカーでも国産小麦商品が発売されるようになりました。
湿気や水問題に弱い小麦の生産量を上げていくことはとてつもなく困難だと思いますが、その活動を支える補助金制度もあり、それ以上に生産者たちの熱い思いが国産小麦市場を支えています。
政府がすべての外国産小麦(輸入小麦)を買い付ける理由
前回のブログで輸入小麦は一括して政府が買い取り、そこから製粉会社に売り渡すという流れがあることを書きました。
政府が大口の購入者となることで、より安定的に小麦を買い付けることができ、食料として重要な小麦の安定供給と小麦を原料とした食品の価格維持が目的。
農林水産省ホームページより
また、政府は売り渡し価格に「マークアップ」と「拠出金」が上乗せした金額を製粉会社は負担します。
「拠出金」は、農水省ではなく、法人が運営する小麦の活動の資金に充てるため、法人に支払います。
(なぜかはよくわかりませんが)その法人の理事のほとんどが複数ある製粉会社の社長や部長が兼任で務めていたりもします。
「マークアップ」とは?
政府が食料として重要な小麦の安定供給と小麦を原料とした食品の価格維持を行うための管理をする管理経費。
小麦自給率を高める・国産小麦を振興するために必要な経費や小麦農家への補助金に充てる資金のことで、輸入小麦1トンあたり約1万6,000千円〜約4万円を上乗せします。
「拠出金」とは?
製粉会社が政府から小麦を買いとる際、奨励金など「拠出金」というものが加算されます。
その額は1トンあたり1530円。年額では75億円もの小麦の「拠出金」が生まれており、使い道は小麦の民間流通への移行や国産小麦の品質向上を目的とする。
この「拠出金」とは法的義務はないものの、製粉会社が支払うことを義務付ける文書「契約生産奨励金取扱要領」を農水省は作成している。
支払い先である財団法人からの支払い済証明がなければ政府から小麦粉を買うことができない仕組み。
一番安いであろうマークアップ(16000円/トン)で計算すると、輸入小麦を合計493万トン政府が買い付けた場合
「マークアップ(約788億円)」+「拠出金(約75億)」= 約863億円を、製粉会社は年間で政府に支払っている計算となります。※令和3年の資料(過去5年の平均数値)
ですが、政府を通さずに直接輸入小麦を買おうとすると関税(252%)が発生してもっと高い金額を請求されてしまうため、政府から買わないという選択はない(というかできないのが現状)です。
製粉会社も赤字ではやっていけないので、小麦の販売価格を高くして利益を出すのです。
年間にして、約863億もの資金。
これが毎年、国産小麦の自給率を良くしていく為に使えるお金の額です。
この大金が動いて、今日の小麦市場が成り立っているのです。
製粉会社がほぼ強制的に支払う「拠出金」の使いみち

マークアップとは別に75億のお金「拠出金」の使いみちにについて、わかりやすい資料がありました。
2008年8月23日の「報道特集NEXT」という番組です。
拠出金を集める法人と製粉会社の暴露を報道記者が追跡した内容で、タイトルは「追跡!小麦で潤う“天下り法人”のカラクリ」という放送でした。
拠出金を集める会社に「財団法人製粉振興会」と「社団法人全国米麦改良協会」が出演しています。
現在の小麦流通量や、公表されている令和版の決算書など交えて提示しています。
一般財団法人製粉振興会の場合
「報道特集NEXT」「追跡!小麦で潤う“天下り法人”のカラクリ」より抜粋。
拠出金とはどういうものですか?
大昔の経緯は私もよく存じ上げないが、今は(小麦の)民間流通への移行と国産麦の品質向上を目的にしていると聞いています。
また生産者や製粉業者への助成金にあてたり、北海道など遠隔地で採れた小麦を本州の製粉会社が引き取る際、輸送費を助成するなどの事業も行っています。
他にも拠出金の使いみちを確認すると、紹介されていたのは、
ビルの一角には製粉振興会のPRコーナー「コナちゃんコーナー」があり「パンができるまで」をコナちゃんが説明するパネルが展示されています。




一般財団法人製粉振興会の年間の諸経費
コナちゃんコーナーなどの宣伝広告費に年間約4300万円。
この場所に来れば、コナちゃんが小麦のことを紹介するパンフレット・DVDなど無料で貰うことができます。
ちなみコナちゃん人形の写真は、とあるブロガーさんが唯一撮影されていた画像で、他の資料はメルカリ、ヤフオクで、1000円以上で出品されている画像を拾ったものです。
これら資料の発行費だけで年間370万円。
また料理教室なども開催されており、小麦粉を使った料理を教えているそうです。
料理教室には年間約3000万円。HPにも小麦粉を使ったレシピが掲載され無料で見ることができます。
製粉振興会のHP:http://www.seifun.or.jp/
ホームページから決算書も覗くことができます。
人件費では役員報酬:約1900万円/年、職員給料:約2000万円以上/年、賞与も退職金も福利厚生も手厚く最高の職場環境です。(羨ましい)
バックナンバーで確認すると20年前からHPは動いてるのですが、サイト来訪者は9,000人程…。
ちなみに、当店(ひとぱん工房)のツイッターフォロワーさんは1年半で1万人越えしてます。
(お陰様です、ありがとうございますm(_ _)m)
社会貢献目的で設立された財団法人(というか公益法人と言えるでしょう)の中身がこうなると、製粉会社のインタビューであったように「活動自体が暗黙の無駄、要は天下り先なんでしょうね」と言われても仕方ないかもしれないですね。
社団法人全国米麦改良協会の場合
常勤の役員と職員10人のうち7人が農水省出身という法人で、製粉会社から集めた拠出金を生産者団体に分配する事業や、国内産麦の研究開発支援を行っている社団法人です。
全国米麦改良協会の仕事の一つは小麦のランク付け。
助成金はこのランクに合わせて支払われるのですが、実際に小麦の品質調査は外部の分析機関に任せているので、やっていることといえば書面での審査が中心になるようです。
理事の年収は約1,600万円で、これも一部は小麦の拠出金から。
「報道特集NEXT」「追跡!小麦で潤う“天下り法人”のカラクリ」より抜粋
農水省から再就職した人の人件費になっているのでは?
そういう業務にある程度、通暁(つうぎょう)している。
単に”天下り”うんぬんということで受け取られるのは、おかしいんじゃないか。
誰がやっても金はかかるんだと思います。
役員は必ず農水省から来なきゃいけない、と指定席になっているのがおかしいのでは?
うーん、指定席というか、誰か適当な人をという時にどういう採用をするかという問題だと思いますけどね。
全国米麦改良協会HP https://www.zenkokubeibaku.or.jp/index.html
番組のタイトルにあるように、テーマは天下り・無駄な資金の流れ、ということにスポットが当てられているので、このようなインタビュー内容を掲載しました。
実質公益法人でもあるわけですが、日本の社会の為に貢献する立場の人ほど収入が高いという傾向があるので(国会議員とか役員とか)税金や公益が無駄に使われている、なんてことは、小麦だけに限った話ではありません。
大切なのは、どう公益が還元されているのかということに尽きると思います。
外国産の小麦を輸入することで、今の小麦産業が成り立っているということが浮き彫りになりました。
中には無駄使いとも言えることがあるかもしれません。
でも、大切な研究費や助成金であったりもします。
このブログを読んでいるあなたは、この政府による買い付けシステムを知って、どう思いましたか?
ぜひ、考えるひとつのきっかけになれば嬉しいです。
上がり続ける小麦価格
輸入小麦の国際価格に、マークアップ、拠出金も上乗せしての今の市場価格。
つまり外国産小麦って・・本当に本当に、安いですね(^_^;)
政府の上乗せがなければ、いったいどんな価格になるのでしょうか。
小麦の未来、自給率向上など、政府に采配権が委ねられているので、消費する私達(製粉会社・仲卸・小麦を使う事業者・消費者)は、政府は何にどういう意図で、使っているのか?を知ることは、とても大切だと思います。
全ての始まりは政府の買付けシステム、その結果、行き着く場所は良いも悪いも消費者なのですから。
この2021年10月、政府売り渡し価格がが前期に比べ19%もアップしました。理由は以下の3点と言われています。
- 年初来の米国産、カナダ産小麦に対する中国の旺盛な買付け、特に高騰したとうもろこしに代替する飼料用需要などで、小麦の国際価格が上昇していること
- 2021年6月以降、米国北部及びカナダ南部の日本向け小麦産地において高温乾燥により作柄が悪化し、価格が高騰していること
- 太平洋エリアで輸送需要が回復傾向になったほか、コロナ禍でコンテナ船など船不足が置きて海上運賃が大幅に上昇していること
すでに小麦の値上がりを実感されている方も多いのではないでしょうか?(当店も2022年7月に一部商品の値上げを余儀なくされることになりました。)
一時的な原因で起きてしまっている値上がりを、市場価格を安定させるためのマークアップが役に立っておらず、ガッツリ政府売り渡し価格が値上げしてて、個人的にはうーん、って感じです。
外国産小麦を使っている仲卸、製造者などは、ただでさえコロナ禍の影響もあるので、このタイミングでの値上げは厳しいのではないでしょうか。
でも存続するために仕方ない措置ですね。
ひとぱん工房のパンの単価は、1つ100円〜300円くらいが売値の相場です。
たかが1円、されど1円の世界なのです。
800億以上のお金は、1円たりとも無駄にならずに動いてほしいと思います。
美味しい国産小麦の認知が広がり、今より少しでも国産小麦が安価に出回り、小麦の消費を少しでも自国の粉で賄えることができたら、、
ひとぱん工房は、その未来を創るため、日々国産小麦のパンを販売しています。
ここまで読んでくださり、ありがとうございました。
次回は、実は国産小麦農家は実はとっても稼いでいる?というお話をしたいと思います。