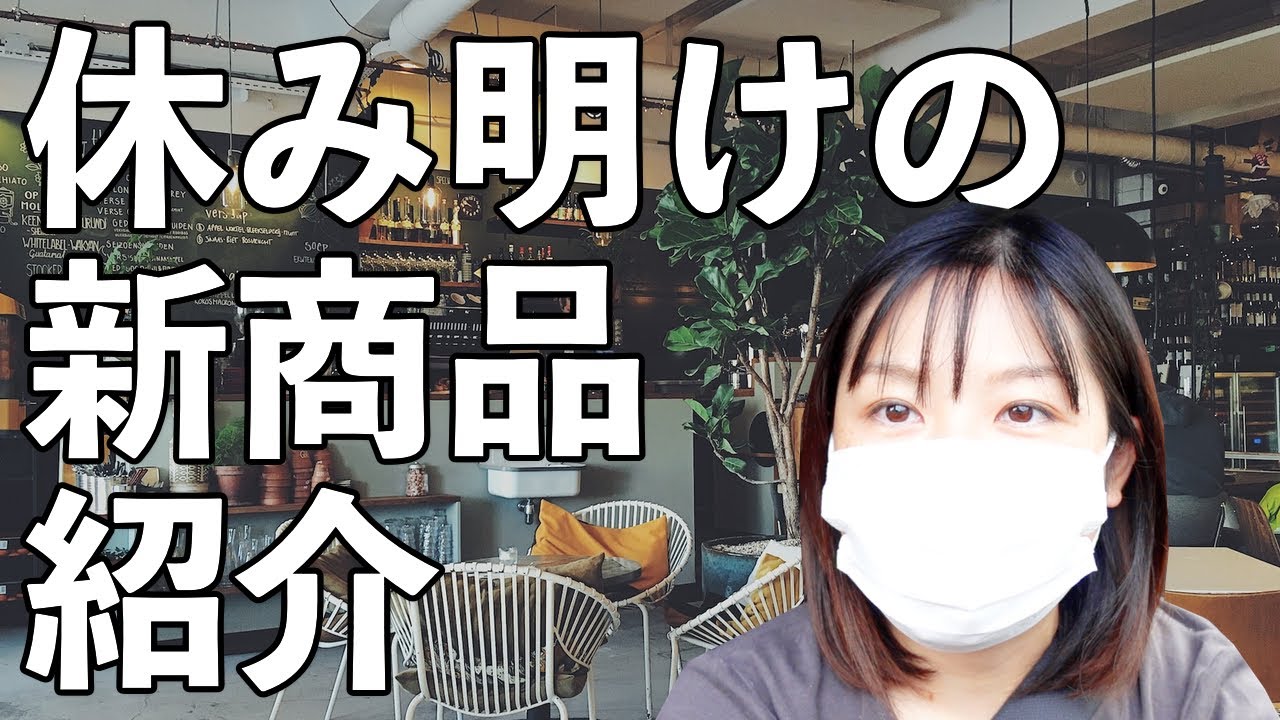静岡の山奥で見つけた理想のパン屋さん「ラトリエ・テンポ」薪窯と自家製小麦に込めた職人の情熱と、私が目指す「日常のパン」とは
先日、お休みを利用して、静岡県にあるパン屋さん「ラトリエ・テンポ」さんへ行ってきました。
市街地から離れた自然豊かな山の中にひっそりと佇む、まるで物語に出てくるような素敵な場所でした。ご主人がご自身で設計し、作り上げたという薪窯。そして、お店の隣の畑で自家栽培している小麦。
パン作りへのまっすぐな情熱と、美味しさを追求する姿勢に、同じパン職人として深く感銘を受けました。
この訪問を通して、ラトリエ・テンポさんのような「非日常の特別なパン」の素晴らしさに触れると同時に、私たち「ひとぱん工房」が目指すべき「日常に寄り添うパン」の役割を再確認することができました。
今回は、その旅で感じたこと、考えたことを皆さんと共有したいと思います。
きっかけはGoogleマップで見つけた一枚の写真

パン屋の休日は、やっぱりパン屋巡りをしてしまいます。新しい発見や学びを求めて、いろいろなお店のパンを食べるのは、私にとって大切な時間です。
今回、静岡方面でどこか素敵なパン屋さんはないかなとGoogleマップで探していたとき、ふと目に留まったのが「ラトリエ・テンポ」さんでした。
最近は本当に便利で、Googleマップ上でお店の名前をタップすると、たくさんの方が投稿してくださった写真を見ることができますよね。私もいつも、その写真を頼りにお店を選んでいます。
たくさんのお店が並ぶ中、ラトリエ・テンポさんのパンの写真は、なんだか他とは違う力強いオーラを放っているように感じたんです。しっかりと焼き込まれたパンの色、その佇まいから「これは何か特別なこだわりがあるに違いない」と直感的に惹かれました。
いわゆる「街のパン屋さん」の親しみやすい雰囲気も大好きなのですが、その写真からは、粉や製法にとことんこだわっている、職人さんの魂のようなものが伝わってきたのです。
「ここは絶対に行きたい!」
そう思い、車を走らせて静岡の山の中を目指すことにしました。
大自然に抱かれたパン工房と、手作りの「薪窯」

お店に到着して、まずそのロケーションに感動しました。浜松の市街地で10年間お店を営まれた後、ご自身の作りたいパンのこだわりを実現するために、この山の中へ移転されたそうです。
緑の木々に囲まれ、きれいな水が流れ、工房の周りには小麦の香りが漂っている…まさにパン作りのための理想郷のような場所でした。
そして、お店の心臓部であるオーブンを見せていただき、さらに驚きました。そこに鎮座していたのは、ご主人がご自身で設計されたという手作りの薪窯オーブンだったのです。
ブロックを一つひとつ積み上げて作られたであろうその窯は、ただの道具ではなく、まるで生きているかのような存在感を放っていました。
ご主人からお聞きした話では、夏場は工房内のエアコンがすぐに壊れてしまうため設置しておらず、室温が50度近くになることもあるのだとか。薪窯から立ち上る熱気と、工房内にほんのりと漂う薪のすすの香りが、その過酷さと、そこから生まれるパンの温かみを物語っているようでした。
快適とは言えない環境かもしれない。でも、そのすべてが「美味しいパンを作る」という一点に集約されている。その潔さと情熱に、ただただ圧倒されました。
究極のパン作りへの挑戦。自家栽培の小麦畑
工房の隣には畑が広がっていて、そこで小麦やライ麦を育てていると伺いました。
まだ土壌がパン作りに適した状態ではないため、収穫した麦でパンを焼くのはこれからの挑戦だそうですが、いずれは自分の手で育てた小麦でパンを焼きたい、とご主人はおっしゃっていました。
「自分で育てた麦でパンを作る」
それは、多くのパン職人が一度は夢見る、究極の姿かもしれません。
効率や生産性を考えれば、決して簡単な道ではないでしょう。天候に左右され、安定した品質の小麦を収穫できる保証もありません。でも、そこには「自分のパンの始まりから終わりまで、すべてに関わりたい」という、純粋で力強い想いがあります。
このお話を聞いたとき、私は北海道で出会った、パン屋さん「風土火水」のことを思い出しました。風土火水も、災害が起きてもパンが作れるようにと、電気を使わず、すぐそばで採れた小麦を使い、薪だけでパンを焼く環境を整えていました。
ビジネスの視点で見れば、非効率的に見えるかもしれません。でも、そこには数字では測れない「ロマン」があります。
市街地を手放す「勇気」と「決断」

ラトリエ・テンポのご主人は、アクセスの良い市街地で10年間築き上げたお店を手放し、この山奥へ移転するという大きな決断をされました。
私たち「ひとぱん工房」も、もうすぐ東松戸へ移転します。たった5年という短い期間でしたが、それでも常連のお客様からは「遠くに行っちゃうの?」と寂しがるお声をたくさんいただきました。
お客様との繋がりを考えると、移転は本当に悩ましい決断です。ましてや、10年間も愛されてきたお店を、簡単には通えなくなる場所へ移すというのは、想像を絶する勇気が必要だったと思います。
でも、それは「お客様を捨てる」ということでは決してありません。よりクオリティの高い、本当に美味しいパンを届けることで、お客様に応えたいという、さらなる情熱の表れなのだと感じました。
短期的な結果や集客のしやすさを手放してでも、長期的な視点でご自身の理想を追求する。その決断力と、パン作りへの深い愛情に、私は心から敬意を表します。
薪窯パンはなぜ美味しい?その秘密は「灰分」にあり

さて、実際にいただいたカンパーニュが、もう本当に絶品でした。口に入れた瞬間に広がる、ほのかな薪の香り。これはガスオーブンや電気オーブンでは決して出せない、薪窯ならではの特別な風味です。
そして、ハード系のパンの美味しさを左右するのが、小麦粉に含まれる「灰分(はいぶん)」という成分です。
あまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、「灰分」とは小麦に含まれるミネラル分のこと。小麦の粒の外皮や胚芽の部分に多く含まれていて、パンの風味や味わいの深さに繋がります。
一般的に、私たちが食パンなどでよく使う強力粉よりも、フランスパンやカンパーニュなどのハード系のパンに使われる小麦粉の方が、この灰分の量が多いのです。
そして、この灰分は、高い熱でしっかりと火が通るほど、その美味しさを発揮します。
薪窯は、電気オーブンなどよりもはるかに高い火力を持ち、特に遠赤外線の効果でパンの芯まで効率よく熱を届けます。これにより、パンの外側(クラスト)はカリッと香ばしく、内側(クラム)は水分を保ったままもっちりと焼き上がるのです。
ラトリエ・テンポさんのカンパーニュを食べて、「側(がわ)が美味しい!」と心から思いました。バゲットのように、クラストの部分が多いパンが好きな方は、きっとこの感覚をわかってくださるのではないでしょうか。
もちろん、中のもちもちした部分も、フルーツなどが入っていて最高に美味しいのですが、薪の香りをまとったカリカリのクラストにこそ、旨味が凝縮されているように感じました。これこそが、薪窯と、灰分の高い小麦粉が織りなす究極のマリアージュなのだと実感しました。
「非日常のパン」と、私が目指す「日常のパン」

ラトリエ・テンポさんのようなパンは、私にとって「非日常の、特別なパン」です。
わざわざ時間をかけて車を走らせ、その場所の空気や景色と一緒に味わう。パンを食べるという行為そのものが、一つのイベントになるような、そんな特別な価値があります。
「あのパンが食べたくなったから、次の休みにまた静岡まで行こうか」
そんな風に、多くの人を惹きつける魅力に溢れています。
一方で、今回の旅を通して、私たちが「ひとぱん工房」で作りたいパンの姿も、より明確になりました。
私が目指しているのは、皆さんの生活にそっと寄り添う「日常のパン」です。
国産小麦の美味しさを、もっとたくさんの人に知ってほしい。毎日でも安心して食べてもらえるような、食卓の主役になれる食事パンを届けたい。
それが、私が「ひとぱん工房」を始めた時からの変わらない想いです。
そのためには、ラトリエ・テンポさんのように究極を追い求める道とは少し違うアプローチが必要だと考えています。
いつでも気軽に立ち寄れる場所にあって、毎日でも買えるような価格帯で、最高の食事パンを提供する。
それが、「国産小麦をしっかりと普及させる」というミッションを持つ、私たちの役割なのだと再確認しました。
これからも、東松戸の地で
だから、私たちは次の移転先である東松戸で、しっかりと根を下ろしたいと思っています。
よほどのことがない限り、例えば「隕石が落ちてきた!」とか(笑)、そういうレベルの出来事がなければ、ここからまた遠くへ移転することはないでしょう。
もし将来、新しい挑戦をしたくなったとしても、それは東松戸のお店を大切に続けた上での「2号店」という形になると思います。
まずは、新しいお店で、これまで以上に皆さんの日常に寄り添えるパンを焼き続けていくこと。それが今の私の目標です。
今回の静岡への旅は、素晴らしいパンとの出会いだけでなく、自分たちの進むべき道を改めて照らしてくれる、本当に貴重な経験となりました。
ラトリエ・テンポさん、素晴らしいパンと感動をありがとうございました。ごちそうさまでした!
私たちも、千葉で頑張ります。