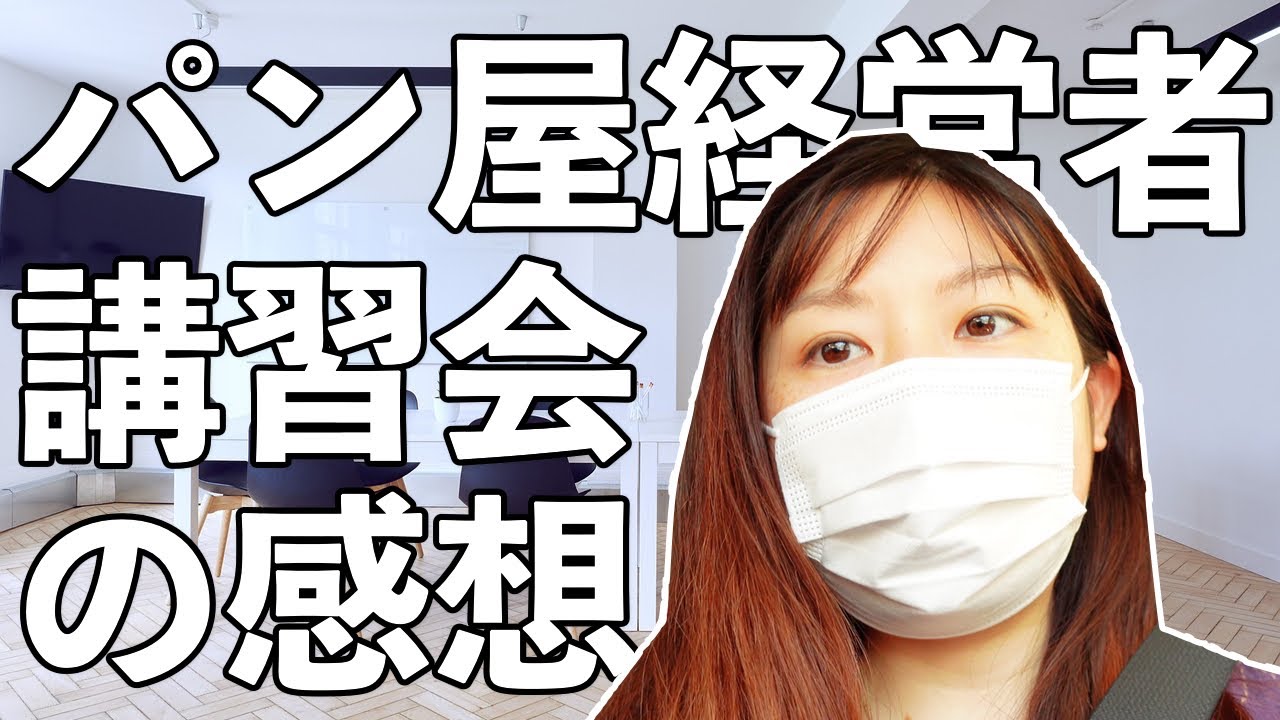パン屋の仕事で一番難しいのは?プロが語るパン作りの奥深さと東松戸への移転準備
皆さん、こんにちは!「ひとぱん工房」のひとみです。
いよいよ東松戸への移転まで4ヶ月を切り、準備も本格化してきました。現店舗(市川店)は、工事のスケジュールの兼ね合いで、2025年1月の3週目まで営業できることになりました(※1月の3週目の土日まで)。
当初お伝えしていた「2025年内いっぱい」から少し延びましたので、ぜひお立ち寄りください。
さて、新店舗に向けて機材の選定や計画と並行して、今一番力を入れているのが「スタッフ育成」です。
新しいお店では、生産量も今よりずっと多くなります。それに伴い、新しいスタッフにも入っていただいているのですが、今回はパン屋さんの仕事、特に「パン作りで一番難しいのはどの工程か?」という、プロの裏側のお話をしたいと思います。
移転準備、進んでいます!
改めまして、こんにちは。「ひとぱん工房」のひとみです。
いつもお店にご来店いただいたり、YouTubeをご覧いただいたり、本当にありがとうございます。
東松戸への移転まで、いよいよ4ヶ月を切りました。
(このブログを書いている時点での話なので、もしかしたら、あっという間に時間は過ぎていくかもしれませんね!)
「今の曽谷店はいつまで営業ですか?」とお客様からもよくご質問をいただきます。当初は「今年いっぱい(2024年12月まで)です」とお伝えしていました。
ですが、工事のスケジュールが少し変更になりまして、2025年1月の3週目まで、今の場所で営業予定となりました。
具体的には、年始のお休みの後、「2週目の土日」と「3週目の土日」に営業します。
3週目の営業が終わると、機材の搬出などが始まる予定です。
あと数ヶ月となりますが、最後まで心を込めてパンを焼いていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
新しいお店に向けた「スタッフ育成」
さて、移転に向けては、新しいオーブンやミキサーなどの機材を選んだり、店舗レイアウトの計画を立てたりと、やることは山積みです。
ですが、それと同時進行で、今まさに力を入れているのが「スタッフ育成」です。
新しいお店は、今の曽谷店よりも規模が大きくなり、パンの生産量も格段に増えます。
そのためには、私一人だけではなく、スタッフ皆さんの力が必要不可欠です。
ありがたいことに、新しいスタッフさんも少しずつ加わってくれているのですが、ひとぱん工房では未経験からスタートするスタッフも多いです。
パン屋さんのお仕事というのは、本当にたくさんの工程があります。
まずはパンの「生地に触れてもらう」というところからのスタートです。
パン作りには、「生地を仕込む」ポジション、「生地を丸める」ポジション、「形を作る(成形する)」ポジション、「オーブンで焼く」ポジションなど、色々な役割分担があります。
まずはその中のポジションを、今の曽谷店の生産規模で一通りできるようになってもらう、というのを目標に、日々練習を重ねています。
パン屋さんのお仕事、一番難しいのは?
ここで皆さんに質問です。
パン屋さんの「パン作り」の工程の中で、どれが一番難しいと思いますか?
- 仕込み(粉や水、酵母などを混ぜて生地を作ること)
- 焼き(オーブンでパンを焼くこと)
- 成形(生地を丸めたり、形作ったりすること)
どれも専門技術が必要ですが、私が思う「難易度の順番」や、その理由についてお話しさせてください。
比較的マニュアル化しやすい「仕込み」
まず「仕込み」です。
これは、小麦粉にお水、酵母(イースト)、お塩などを加えて、ミキサーという大きな機械でこねて「パン生地」を作る作業のことです。
もちろん、その日の気温や湿度によって配合を変えたり、生地のこね上がり具合(「グルテン」がどれくらいできたかな?とか)を見極めたりする「職人の目」は必要です。
ですが、作業の多くは、
「この粉を何キロ、ボウルに移す」
「お水を何リットル、ミキサーに入れる」
「ミキサーのボタンを押す」
といった、マニュアルがあれば比較的、誰でも取り組みやすい作業でもあります。
今のミキサーは高性能なので、「1速(低速)で何分、2速(中速)で何分」というように回す時間や速さを決めておけば、材料が大きく変わらない限り、大体いつもと同じような生地に仕上がってくれます。
もちろん「見極め」は大切ですが、他の工程に比べると、パン作りの経験が浅い人でもスタートしやすいポジションかな、と私は思っています。
頭脳と体力勝負の「焼き」
次に「焼き」のポジション。これは「焼成(しょうせい)」とも言います。
発酵(ふくらませること)が終わった生地をオーブンに入れて、こんがり焼き上げる、パン屋さんの「花形」とも言える仕事ですね。
この「焼き」のポジション、実は「覚えることがめちゃくちゃ多い」んです。
まず、今オーブンに入っている生地が、何のパンになるのかを全部覚えていないといけません。
「あ、この丸い生地は『バターシュガー』だな。じゃあ、焼き上がる前にカットしてバターと砂糖を乗せなきゃ」
という感じです。
そして、一番の難しさは「組み立て力」です。
パン屋のオーブンは家庭用のものとは違い、一度にたくさんのパンを焼きますが、それでも限界があります。
次から次へと発酵を終えたパンが「焼いてー!」と順番待ちをしています。
- 「今、オーブンにはAのパンが入っている」
- 「Aのパンはあと3分で焼き上がる」
- 「その次に控えているBのパンは、Aのパンより低い温度で焼くから、Aが出たら温度を調整しないといけない」
- 「Cのパンは、Bのパンを入れた5分後くらいに発酵が終わるな…」
こんな感じで、何十種類ものパンの焼き時間、温度、次の発酵のタイミングを頭の中でパズルのように組み立てる必要があります。
「オーブンの中に何も入っていない時間(空いている時間)」をなるべく作らないように、いかに効率よく、無駄なく、そして美しくパンを焼いていくか。
常に先の先を読み、オーブンの前で素早く動く…「先読みの力」と「体力」がものすごく必要な、頭脳戦のポジションなんです。
ただ、この「焼き」も、「パンを焼き切る」という明確なゴールがあります。
毎日繰り返していけば、「次はこれが来るな」というのが体に染み付いていきます。
覚えることは多いですが、慣れと経験でカバーできる部分も大きいという意味で、私は「成形」よりはまだ易しいかな、と思っています。
プロが語る最難関:「丸め」と「成形」
そして、私(ひとみ店長)が、パン作りにおいて一番難しく、一番時間がかかると思っているのが、「丸め」と「成形」です。
特に「成形」は、本当に奥が深いです。
1. すべての基本「丸め」
「丸め」というのは、分割したパン生地を、文字通り「丸くする」作業のことです。
「え、ただ丸くするだけでしょ?」
と侮ってはいけません。これが、パンの「基礎中の基礎」であり、未経験者にとっては最初の大きな壁なんです。
「丸め」の目的は、ただ丸くすることではありません。
生地をこねる時にできた大きなガス(炭酸ガス)を均一に抜き、生地の表面を「つるっと」滑らかに張らせることです。
この「丸め」がうまくできないと、どうなるか?
- 表面がデコボコだと、その後の発酵でいびつに膨らんでしまう。
- 生地の張り(テンション)が弱いと、焼き上がった時にパンがダレて、平べったい形になってしまう。
- 逆に強く締めすぎると、生地(グルテン)が傷んでしまい、うまく膨らまなくなる。
パン屋さんでよく使う言葉に、「生地が締まる」とか「腰がつく」という感覚があります。
これは、生地を優しく、しかし確実に丸めることで、生地に適度な弾力(=腰)が生まれる感覚のことです。
この感覚は、頭でイメージして分かっていても、手がそうならないんです。
本当に、スポーツや楽器の練習と同じで、数え切れないほど生地に触れて、その「手の感覚」を覚えるしかないんですね。
この「丸め」という基礎ができて、初めて次の「成形」に進むことができます。
2. もっとも難しい花形「成形」
そして、私が思う最難関が「成形」です。
「成形」とは、丸めた生地を、あんパンやクリームパン、メロンパン、食パン、バゲットなど、そのパン独特の形に作り上げていく作業です。
これは、「丸め」以上に繊細な技術が求められます。
生地を傷めないように優しくガスを抜きながら、均一な形に整えていく…。
この「成形」ポジションは、お店のパンの「見た目」をすべて決めると言っても過言ではありません。
そして、この技術の習得には、本当に長い年月がかかります。
センスがあっても3年かかった
少し私の話をさせていただくと、私は幸いなことに、一番最初のパン屋さんに入った時、成形や丸めは「その日である程度できたね」と言われるくらい、センスが良かった方(と、自分では思っています(笑))だったんです。
でも、そんな私でも、あらゆる種類のパンの成形を、一通り「ちゃんと」「きれいに」できるようになるまでには、3年はかかりました。
そして、パン屋を何年も続けている「今」でも、まだ成長中だと感じています。
「あ、前はうまくできなかったけど、今日の方がもっときれいにできたな」
「こういう生地の時は、こっちの方がいい形になるな」
という発見が、毎日あるんです。
それくらい、「成形」というのはゴールがない、奥深い世界なんですね。
なぜ「成形」がそんなに大事なの?
「丸め」と「成形」がうまくできていないと、それは「焼き」にそのまま出てしまいます。
例えば、生地の締め方が均一でないと、発酵した時にいびつな形で膨らんでしまいます。
当店の「栗あんぱん」は、その名の通り「栗」の形をしています。
でも、成形がうまくできていないと、生地がダレてしまって、全然栗には見えない、平べったいパンになってしまうんです。
パン屋さんって、よく「あっちのパンの方が大きくない?」とか「ちょっと形が違うね」ってこと、ありませんか?(笑)
お菓子屋さん(ケーキ屋さん)だったら、ショートケーキの大きさが全部違ったら大変ですよね。絶対にそんなことはないと思います。
でも、パン屋さんは、生地を分割する時の重さ(グラム)は全部一緒でも、成形する人の技術によって、「見た目の形」や「膨らみ方」が変わってしまうことが、”あるある”なんです。
- こっちはキュッと締まってて、小さいけど密度が濃そう。
- こっちはふんわり膨らんでて、大きく見える。
(※重さは一緒なんですけどね!)
もちろん、私たちプロは、「常に同じクオリティのものをお届けする」ことを目指しています。
「今日は形が悪いからいいや」ではなく、全スタッフが同じレベルでできるように、日々切磋琢磨しています。
ただ、それくらい「成形」という作業は、熟練の技術が必要で、特に未経験のスタッフがすぐにマスターできるものではない、ということです。
新しいお店に向けて、2年、3年かかる技術を、今まさにスタッフに伝えている最中です。
お客様へのお願い:成長を温かく見守ってください
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
私たちが今、新店舗に向けてどんな準備をしているか、少し伝わりましたでしょうか。
新しい東松戸のお店では、たくさんのスタッフが働いてくれることになります。
その中には、パン作りの経験が浅く、今まさに「丸め」や「成形」を必死で練習しているスタッフもいます。
もしかしたら、オープン当初は、
「今日のあんぱん、ちょっと形がいつもと違うかも?」
「塩バターぱんの巻きが、ちょっとゆるいかな?」
なんてことが、あるかもしれません。
もちろん、お店に出す前に、最終的には私(店長)がすべてチェックをして、「これなら大丈夫!」というものをお出しします。
でも、どうしても、何年もやってきた私やベテランスタッフが作るものと、全く同じクオリティにするには、時間がかかってしまうのも事実です。
ですから、もしよろしければ、新しいお店にいらした時には、そんなスタッフたちのことも、ちょっとだけ温かい目で見守っていただけたら嬉しいです。
「あ、このパンは今、練習中のスタッフさんが作ったのかな」「頑張ってるな」
という感じで、スタッフの成長の過程も一緒に楽しんでいただけると、私たちも本当に励みになります。
季節の変わり目、ご自愛ください
さて、今日はパン屋さんの「裏側」、特に「成形」の難しさについて、熱く語ってしまいました。
(ここまで読んでくださった方、本当にありがとうございます!)
ブログを書いている今は、だいぶ肌寒くなってきましたね。
季節の変わり目は、風邪を引いたり、体調を崩しやすかったりします。
油断せず、暖かくしてお過ごしくださいね。
私たちも、移転準備と日々の営業、体力勝負の日々ですが、体調管理に気をつけて乗り切りたいと思います!
それでは、また次回のブログでお会いしましょう!
おつぱんでーす!