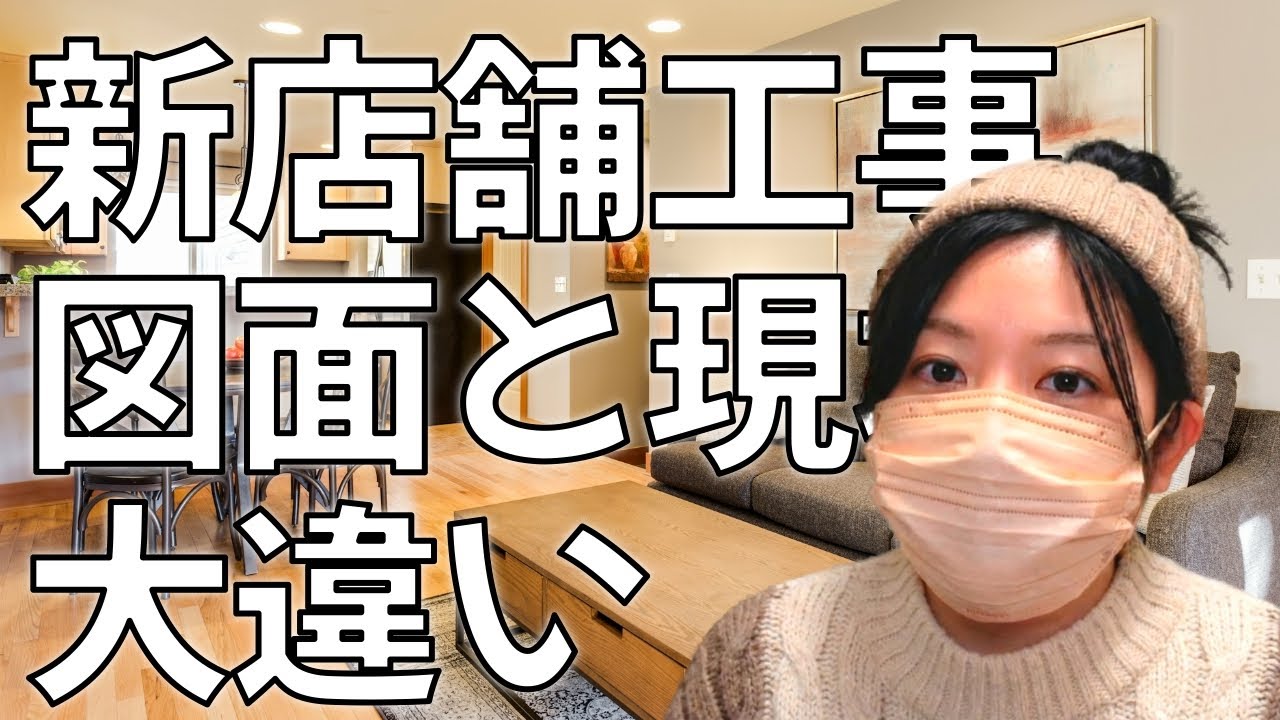食品の裏側を知る大切さ【安部司 氏の本】
食の安全性についての情報の取り方
食材の安全性、危険性について、どう学んでいるんですか?
食に関係ない分野で活躍されている方でも、意外と食の話をされることがあります。
食べることは生きることに密接ですからね。
飲食関係はもちろんですが、関係なさそうな医者、介護職、看護師、整体師、ダイエッター、子育てママ、心理カウンセラー、スピリチュアル、経済アナリストなどなど、多岐に渡る分野で活躍されている方々の情報発信の中で、食と関係している部分があったりします。
私は食にはアンテナ張ってますので一通り聞くようにします。
事実かどうかはさておき、情報はあればあるだけいいです。
また食べることは生きることなので、お金の流れと密接に関わっています。
お金の話をすると話しが逸れますのでまた今度。
情報の点と点が結ばれて、自分の体験、お金の流れ、ファクト、根拠が繋がってきて、ようやく安全性、危険性を判断しようと思います。
それでも真実は複雑で、決めつけることはできないのですが。
私の作る「ひとぱんの安全性」の根拠の一番大きな要は私の体験です。
「パンを食べた後胃もたれしない」という私の体験がパンによく配合される油によって私の体が反応していることを知り、
その体験から自信をもって「トランス脂肪酸を避けよう」と呼びかけているわけです。
でも、気にならない人はどっちでもいいのです。
求める人がいらっしゃるから、現にお店が継続できており、同じ体験をしている方が他にもいるということです。
一番大切なのは、あなたの体の反応だということをお伝えしたいと思います。
安部司著「食品の裏側」との出会い
食の安全性について、影響を受けた人はいますか?
「食品の裏側」という本を書いた安部司さんが思い浮かびました。
食に興味がある方は知っている人も多いと思います。
「食べてはいけない」シリーズの本を見たことないでしょうか?
私は本で安部さんを知りましたが、講演会活動もされているので、それで知った人とかもいるかもしれないですね。
僕も読んで面白かったのを覚えています。
元添加物販売業社の営業マンで、食品を舐めただけで何が使われているのかがわかる、という人ですよね?
そうです。
添加物の危険を身近で感じるようになり「食べているものに何が入っているのかを知ろう」という活動をされています。
youtubeでも動画が見れると思いますが、化学的添加物の粉末を数種類をサっと調合して見せて、お湯を入れたらあらびっくり。
何の食材も入ってないのに、コクのあるとんこつラーメンのスープを完成させます。
最初はエンターテイメントで面白いと感じるのですが、続いてお子さんが大好きなオレンジジュースや炭酸ジュースが粉からできるのを見て、ゾッとします。
甘くて飲めないものが、添加物によってとっても飲みやすく美味しいに変わるという体験を見ることができます。
最初に体の反応こそが、一番大切だと伝えましたが、添加物は体の門番を騙すことができるのです。
これは、かなり危険なことだと私は思っています。
この添加物に関しては、お金の流れも大きく関わるので問題は複雑です。
危険な食べ物が売られているわけがない、って普通思いますよね(笑)
日本は特に安全性が高そうなイメージも強いです。
私も過去はそう思っていました。
でも事実はそうではありません。
安全性なんてのは、曖昧なものです。
添加物の複合実験はしていない!?
安部さんが警笛を鳴らしていることに、添加物それぞれの安全性はラットを使って数値化、ルール化しているけれど、添加物の複合実験はされてないので、安全だと言えるはずがないとの内容があります。

よく例に挙がるのがミックスサンド。
ミックスサンドって必ずコンビニとかで売られてるサンドッチだよね。
そうです。
パン、マヨネーズかファットスプレッド、トマト、きゅうり、レタス、卵サラダ、ハム、なんかがよくある具の種類だと思いますが、具材一つ一つに添加物が添加されています。
野菜は次亜塩素酸液で、変色止めをしています。
卵、ハムは添加物は多いでしょう。
ハムに添加されている発色剤、亜硝酸ナトリウムは、お肉の成分アミンと結合し、発がん性物質となる化学反応は証明されています。
お肉のグラムに対して使っていい量が厳格に決められているのですが、そもそも発がん性物質を食べようとはあまり思わないですね。
たまに大食いを生業にしている方が、ウインナーを大量に食べているのを見て、心配になってしまいます。
話はそれましたが、具一つ一つに対しての添加物は大丈夫だとしても、全部の添加物を同時に摂取することを想定した実験は行われていません。
添加物の摂取量を把握し、安全なラインを維持していたいと思うのですが現状は不可能です。
日本のルールにキャリーオーバーというのがあるからです。
キャリーオーバーとは?
例えば、ミックスサンドの製造工程に使っていない添加物は記載する必要がないというルールです。
パン、ハム、卵、野菜、全ての食品に含まれる添加物は「合体させたら微量になるだろうから危険性はない」という謎の解釈により、記載義務がないのです。
これをキャリーオーバーといいます。
じゃあ添加物含め、何を食べているのか把握しようがないですね。
ミックスサンドなんて、ペロッと2つくらい食べれてしまいそうですが、添加物の種類・量の側面から考えると、避けたくなるのは私だけではないはずです。
添加物の名前は分かりずらいですよね。
でもよく出会うものは調べたり、覚えるようにしたりしました。
添加物を避けることはできない!?
こういうことを勉強していくとぶち当たるんですけど、もう添加物を全て避けることはできないんです。
食材を自炊しない限り、高い確率で添加物を食べることになります。
知識をつけて少しでも避けることで、減らすことはできると思います。
これを10年、20年続けていくと、大きな差になると思いますね。
添加物表記なんて難しいことを考えなくても、体の反応に意識を向けることをおすすめします。
私のように「胃もたれする」も立派な反応ですし、見落としがちな小さな症状、頭痛、目がしょぼしょぼする、便秘、または下痢、末端が冷えやすい、ゲップがよく出る、疲れる、眠くなる…などなど。
メンタルでは、イライラしやすい、落ち込む、やる気が出ない、気持ちの切り替えができない…などなど。
食と心は深い繋がりがあるのは間違いないです。
お腹空いてるとイライラしますしね(笑)
体は素直なので、食べた後に必ず起こる不調反応があれば注視すべきでしょう。
体の声を無視し続けると、もう反応しても無駄だと思われ、無症状となり、突然大きな病気に繋がったりすることになります。
症状は悪いことではありません、治癒するための反応でもあります。
小さなうちに気づきましょう。
体が喜ぶこと、気持ちいいことを心がけて。
日頃から体を酷使している方も体に感謝の意識を向けるだけで癒されることもあります。
添加物にストレスを抱えるよりも効果大かもしれません。
添加物が悪いわけではない
安倍司さんも添加物を否定はしてません。
添加物は忙しい主婦の方とかの助けになっているヒーローみたいなものですし、社会貢献性は計り知れません。
ただ光だけでなく闇の部分もある。
そこは知識をつけて何を選択するか自分で決めていきましょうねって話ですね。
その通りですね。
選択するのは消費者なので、企業は売れるものをただ作っているだけなんです。
ここに善悪の感情を入れて、企業を責めることはナンセンスですね。
アメリカが癌を減らしたトランス脂肪酸への対策
アメリカ政府のトランス脂肪酸の件は見事だなって思いました。
どういった内容ですか?
アメリカは癌の死者数が多すぎることから国家の危機だと捉え、がん撲滅を目標とする「米国がん対策法」を施行。
食からのアプローチ対策として癌死亡者の食事傾向などを研究し、トランス脂肪酸が発がん性に大きく影響している事実を突き止めました。
ここで難しいのは、トランス脂肪酸を禁止したら油脂メーカーが大量に潰れてしまいます。
アメリカの食事は、油使用率がとっても高いのです。
フレンチフライにフィッシュアンドチップス、ポップコーンに、ステーキソテーなどなどイメージしてもらえたらわかりますね。
バターなんて良質なものは、生産もコストも釣り合わない。
そこで安い大量の油に最適なのが、植物加工油脂です。
コーンとか、大豆とか、広大な土地でいっぱい作れますからね。
原因はその油の加工の際に発生してしまうトランス脂肪酸なので、それが出回り続ける限りがん撲滅は厳しい。
そこで政府は含有量表記を義務付けました。
「トランス脂肪酸含有量◯%」といった具合です。
そして、がんの主な原因がトランス脂肪酸であるという情報が陰謀論ではなくしっかり認知されることとなりました。
政府はそれだけ真剣だったようですね。
普通は情報発信する側も利権を得ていて、なかなか情報が出回らないのですが…。
マクガバン・レポート(がん患者の調査レポート)の功績
また、アメリカの医療補助は弱く、風邪すら高額医療となり病院にお世話にならないよう健康を意識する国民が増えました。
そのような経済的側面もあり、消費者は価格が高くてもトランス脂肪酸0%から1%未満のものを選ぶようになりました。
がん治療で高額な医療費を払うよりも、毎日の健康のための小さな出費の方が安い。
油脂会社は、売れない商品を作り続けることはできません。
結果、米国でのがんによる死亡率は1991年のピーク時から2016年までの25年間で27%減少させることに成功しました。
日本は反比例してがん患者・死亡者は増加しているので、何かアメリカからヒントを得たいものです。
安部司さんは、勇気をもって食の事実と私達に選択肢があることを伝えられています。
私も「食の選択肢があることを世の中に伝えていきたい」と思っています。
これもまた、パン屋をやる1つの理由です。