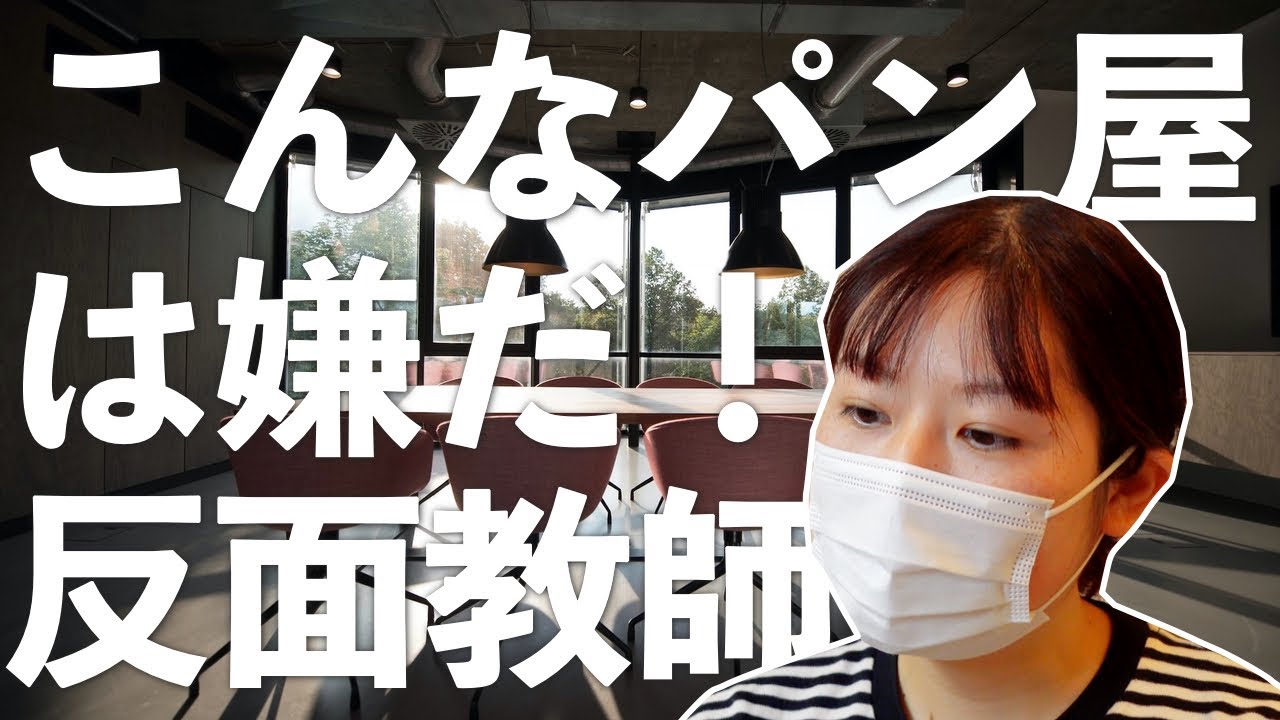【パン屋の裏側】薪窯で焼くパンはなぜ美味しい?本物の職人技とこだわりに迫る旅
今回は、薪窯(まきがま)でパンを焼くパン屋さん「ラトリエ・テンポ」さんの工房を特別に見学させていただきました!
工房に足を踏み入れた瞬間に感じた熱気、そして圧倒的な存在感を放つ薪窯。その窯で焼き上げられるパンが、なぜあんなにも味わい深いのか、その秘密にたっぷりと触れることができました。
ラトリエ・テンポのオーナーさんから伺ったお話を、私の感動と共にお届けします。パンが好きな方はもちろん、ものづくりの裏側や食へのこだわりに興味がある方にも、きっと楽しんでいただけるはずです。
はじめに:美味しいパンが生まれる特別な場所へ
毎日パンを焼いている私ですが、パン作りの世界は本当に奥が深く、まだまだ知らないことばかりです。特に、私が普段使っている電気オーブンとは全く違うアプローチでパンを焼く「薪窯」には、強い憧れがありました。
今回は幸運なことに、静岡県浜松市でこだわりのパン作りをされている「ラトリエ・テンポ」のオーナーさんのご厚意で、工房の心臓部である薪窯を間近で見学させていただける機会に恵まれたのです。
自分の工房とは違う、独特の香り、空気、そして熱気。そこには、パンを愛し、自然と共にパン作りと向き合う職人さんの素晴らしい哲学が詰まっていました。今回は、その感動と学びを皆さんと共有したくて、筆を執っています。
圧巻の存在感!これが本物の「薪窯」

ラトリエ・テンポさんの工房にお邪魔して、まず目に飛び込んできたのが、ずっしりと構える大きな薪窯でした。レンガで丁寧に作られたその姿は、まるで工房の主のよう。
「うわー、すごい…!」
思わず声が漏れてしまいます。窯の入り口は美しいかまぼこ型のアーチを描いていて、オーナーさんご自身で設計された形なのだとか。
このドーム状の天井には、実はとても重要な意味があるんです。窯の中で燃え盛る炎から発せられた熱が、このカーブに沿って効率よく循環し、窯全体に均一に行き渡るようになっているのだそう。まさに、美味しいパンを焼くためだけに考え抜かれた、機能美あふれる構造なんですね。
しかし、その圧倒的なパワーと引き換えに、工房内の環境は想像を絶するほど過酷です。
「夏場、この窯の前は何度くらいになるんですか?」
と尋ねると、
「手前はもう50℃以上にはなりますね。去年は一回、熱中症で倒れましたよ」
と、笑顔で話すオーナーさん。エアコンは薪窯から出る熱や灰の問題で設置が難しく、冷たい水を通す特殊なベストや送風機で暑さを凌いでいるとのこと。美味しいパンの裏側には、こんなにも大変なご苦労があるのだと、頭が下がる思いでした。
なぜ薪窯で焼くとパンは美味しくなるの?電気オーブンとの決定的な違い

さて、ここからが本題です。「薪窯で焼いたパンは美味しい」とよく言われますが、それは一体なぜなのでしょうか?私が毎日使っている電気オーブンと、具体的に何が違うのか、オーナーさんに素人ながらの質問をぶつけてみました。
違い① 焼き上げる力「遠赤外線」
最大の違いは、熱の伝わり方にありました。
電気オーブンの熱が「対流熱(温められた空気が循環して表面から焼く)」がメインなのに対し、薪窯の熱は「輻射熱(ふくしゃねつ)」が主体となります。
薪を燃やすことで窯の内部のレンガや石がじっくりと熱せられ、その石自体が大量の遠赤外線を放出します。この遠赤外線が、パン生地の表面だけでなく、内部にある水分に直接働きかけて、内側から効率よく熱を通していくのだそうです。
「内側から火が入る、というイメージですね。だから、ある程度短時間で焼き上がるんです」
この「内側から火が入る」というのが、薪窯パンの美味しさの最大の秘密。表面が焦げる前に中心までしっかりと火が通るため、パン生地内部の水分を必要以上に飛ばすことなく、しっとりと焼き上げることができるのです。
私たちが薪窯パンを食べた時に感じる、「外はパリッと香ばしく、中は驚くほどもっちり、しっとり」という独特の食感は、この遠赤外線の力によって生み出されていたんですね。
違い② 焼き時間の短縮がもたらす効果
遠赤外線の力で内側から効率よく熱が伝わるため、薪窯でのパンの焼き時間は電気オーブンに比べて格段に短くなります。
例えば、あるパンを焼くのに、一般的なコンベクションオーブン(熱風を循環させるタイプの電気オーブン)だと40分かかるところ、十分に温まった薪窯ならわずか15分~20分ほどで焼き上がることもあるのだとか。
この焼き時間の短さが、先ほどお話しした「パン生地の水分」を保つことにつながります。短時間で一気に焼き上げることで、パンが乾燥するのを最小限に防ぎ、みずみずしく、小麦本来の風味豊かな味わいを引き出すことができるのです。
違い③ 唯一無二の「香り」
そしてもう一つ、電気オーブンでは決して真似のできない、薪窯ならではの魅力が「香り」です。
窯の中で燃える薪。その木が燃える時に立ち上るスモーキーで香ばしい香りが、パン生地にほのかに移ります。これは「燻煙(くんえん)効果」とも呼ばれ、パンの風味に複雑で奥深い味わいをプラスしてくれます。
薪の種類(ナラ、クヌギ、桜など)によっても香りが変わるそうで、まさに自然の恵みそのものをパンに閉じ込めているよう。この豊かな香りは、薪窯でしか味わえない、最高の贅沢かもしれません。
美味しさの源「薪」はどうやって?知られざる調達の舞台裏

素晴らしいパンを焼き上げる薪窯ですが、その燃料である「薪」がなければただの置物です。この薪を、一体どうやって調達しているのでしょうか?
お話を伺うと、そこにも大変なご苦労と工夫がありました。
メインは、知り合いの林業を営んでいる方から、伐採した木を譲ってもらうこと。もちろん、もらえるのは切り倒したままの「丸太」の状態です。それを、自分の手で運び出し、割り、乾燥させて、ようやく薪として使えるようになります。
「丸太を運ぶのが、また大変で。30cmくらいの長さの丸太でも、1個20kg、30kgは軽くありますからね」
想像するだけで、腰が痛くなりそうです…。
もちろん、薪を販売している「薪屋さん」から購入することもあるそうですが、多くは家庭用の薪ストーブ向けのお値段。パン屋のように毎日大量に使うとなると、コスト的にかなり厳しいのが現実です。
だからこそ、地域の方との繋がりを大切にし、時には「木を切ったから、いらないかい?」というお声がけに駆けつけ、自ら丸太をいただきに行くこともあるのだとか。
美味しいパンを安定して焼き続けるためには、燃料である薪をどう確保するか、という地道な努力が欠かせない。その情熱と行動力に、ただただ感銘を受けました。
パン職人の探求心は止まらない!自家製麦への挑戦
オーナーさんのこだわりは、薪窯だけに留まりません。なんと、工房のすぐ隣にある畑で、パンの原料である小麦やライ麦をご自身で育てているというのです!
「1年目は小麦を、2年目はライ麦の種を蒔いて、少しずつですけど収穫もできたんですよ」
お話を伺った時、畑はまだ土が痩せている状態で、作物を育てるのは簡単なことではないようでした。それでも、「色々と工夫して、ここで育った作物を使えるような環境にしていきたい」と、未来を語るオーナーさんの目はキラキラと輝いていました。
自分で育てた麦を使い、自分の手で割った薪で火を熾し、自分で設計した窯でパンを焼く。
これぞまさに、地産地消の究極の形。考えるだけでワクワクしてしまいます。手間も時間もかかる、本当に大変な道だと思いますが、「できることから少しずつ」と着実に前に進む姿に、同じパンを作る人間として、大きな刺激と勇気をいただきました。
自然の力で土を育てる「ライ麦」と無農薬への想い
オーナーさんの自家栽培のお話に深く感動した私は、思わず自分の経験をお話ししていました。
「実は私も、去年北海道の農業法人『アグリシステム』さんのツアーに参加させていただいて、無農薬のライ麦畑を見てきたんです!」
その時に見た光景は、今でも目に焼き付いています。地平線まで続くライ麦畑。品種によっては人の身長よりも高く育つその生命力に、ただただ圧倒されました。
そして何より驚いたのが、ライ麦が持つ「土を耕す力」です。
ライ麦は地上に見えているのと同じくらいの長さの根を、まっすぐ地中深くに張るのだそうです。その力強い根が、硬くなった土を自然に耕し、ふかふかの豊かな土壌を作り出してくれるのだとか。
農薬や化学肥料に頼らず、自然の力を借りて土そのものを健康にしていく。そんな持続可能な農業の在り方を目の当たりにして、パンを作る者として、素材が生まれる背景を大切にしたいと改めて強く感じたんです。
だから、オーナーさんがご自身の畑で、土作りから挑戦されているお話には、本当に共感しかありません。私たちパン屋は、農家さんが丹精込めて育ててくれた小麦やライ麦がなければ、何も作ることができないのですから。
安心して美味しく食べてもらえるパンをお届けしたい。その想いは、きっとどのパン屋さんも同じはず。無農薬という選択は、その想いを形にするための一つの大切な答えなのだと、改めて感じた瞬間でした。
素敵な工房の名前の由来:「ラトリエ・テンポ」と「ひとぱん工房」

最後に、ずっと気になっていたお店の名前の由来についてもお聞きしました。
「ラトリエ・テンポ」という素敵な響き。
「『アトリエ』はフランス語で『工房』。『テンポ』は、ラテン語の『tempus(時)』が語源になっている言葉で、『時間』や『リズム』といった意味があるんです。だから、『時の工房』みたいなイメージですね」
なんとロマンチックな由来でしょう!パン作りには、発酵や焼成など、様々な「時間」が関わってきます。その一つ一つを大切にしたい、という想いが込められているのかもしれません。
そして、会話の流れで私の「ひとぱん工房」の名前の由来も聞かれました。
「店長が『ひとみ』っていう名前なので、もうシンプルにひらがなで『ひとぱん』。それに『工房』をつけようかって話していたのが、そのまま本決まりになったんです(笑)」
ラトリエ・テンポさんの素敵な由来の後だと、なんだか少し照れくさいですが、これも私たちらしくて気に入っています。工房の名前には、それぞれの作り手の想いや人柄が表れるのかもしれませんね。
おわりに:パン作りの奥深さと情熱に触れて
今回の工房見学は、私にとって本当に貴重な経験となりました。
薪窯の圧倒的な迫力と、そこから生み出されるパンの美味しさの科学的な理由。そして何より、一つのパンがお客様の手に届くまでに、どれだけの時間と手間、そして作り手の情熱が注がれているかを、改めて肌で感じることができました。
パン作りは、本当に奥が深い。でも、だからこそ面白い。
ラトリエ・テンポのオーナーさんのように、常に探求心を忘れず、自然に敬意を払い、パンと真摯に向き合っていく。そんなパン職人でありたいと、心を新たにしました。
この記事を読んでくださったあなたも、次にパン屋さんを訪れる時、そのパンの向こう側にある職人さんの顔や、工房の風景を少しだけ想像してみてください。きっと、いつものパンがもっともっと特別な味に感じられるはずですよ。