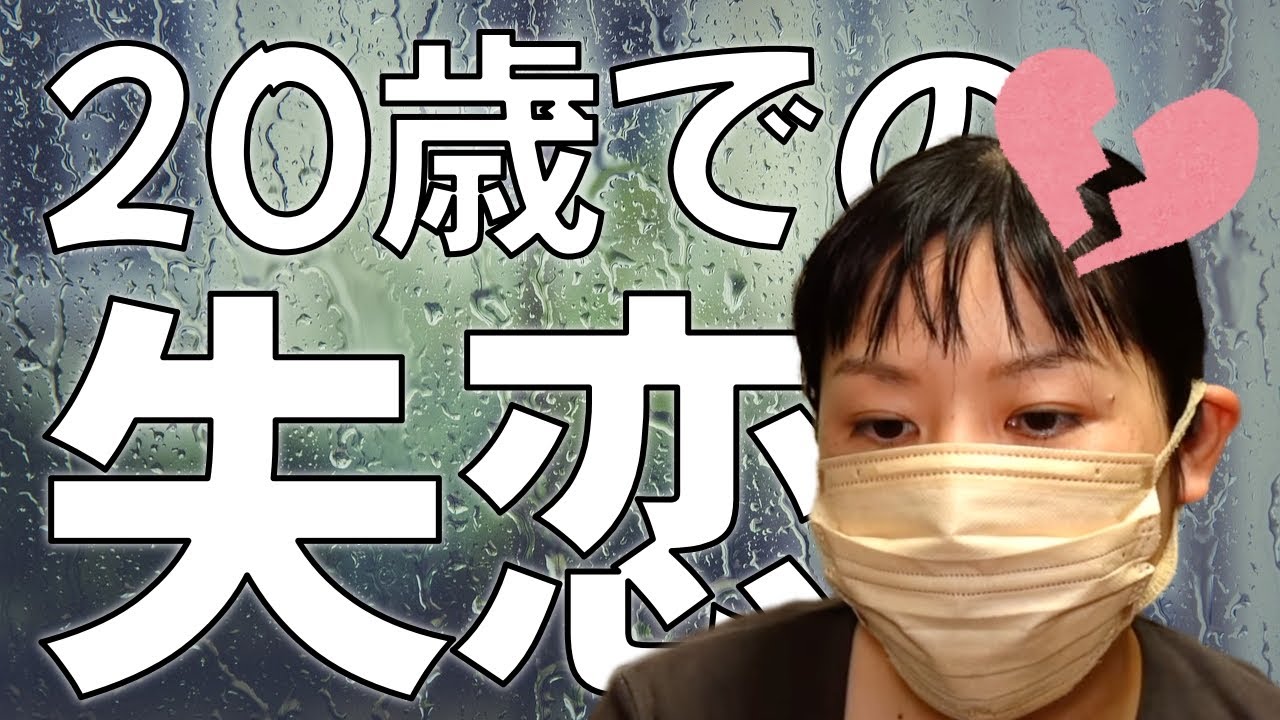パン屋経営者が直面する人材教育の課題とその解決策
経営者になってみて見える世界が変わったりしました?
変わりました、全然違いますね。
パン屋経営者が直面する人材採用の課題とは
私がイメージする「パン屋さんが盛り上がっている」っていうのは、イコール、スタッフが増えるということです。
お客様が増えているのに、パンの生産量が増えていないと、盛り上がるというよりは「維持」という状態ですよね。
まさに、ひとぱん工房も生産量が増やせてないので「維持」しているところなんです。
現状の環境で、生産力を増やすためには、機械性能に頼ることもありますが、やはり1人で作れる量には限界があります。
それに作業スペース、ストックスペースが縛られているともなれば、回転率を上げることしか方法はありません。
回転率を上げる、つまり作業の手を増やすことです。
入社したスタッフは、教育期間があり、実践、失敗、勉強を繰り返し、最低3ヶ月くらいで生産力になってくれます。
長く勤めていただけたら万々歳、覚えた頃に退社したら、さぁもう一度やり直し。
パン屋経営はこの繰り返しです。
スタッフは人なので「失敗したパンの原因は?」というような単純な話ではありません。
様々な原因が重なり合ってスタッフは退社し、常に人員募集し続ける。
というパン屋さんは私が働いてきた中でも少なくはありませんでした。
パン屋だけに限った話ではありませんが。
パン屋のオーナー側からの視点でお話をすると、開業前までは、パンのこと、お金のことなど、「物」に対してずっと向き合ってたものを、突然「人」に向き合わないといけなくなるっていうことに対応できるかできないか、ということに尽きるのではないか、と私は思います。
健康を維持し生産し続けること、経営、同業者・お客様との信頼関係構築、とは別に、人材を雇うということは、まったく違うスキルが必要だと考えています。
ひとみ店長が修行で美味しいパンを作る技術は学んできたけども、経営してみると美味しいパンを作る技術だけではなくて「人をマネジメントする技術」が別で必要になってきたということですね。
そうですね。
まずスタッフが楽しんでいたり、不満なく働けていること。
それがお店にとってすごく重要であることはわかっていましたが、実際経営者になって、こんなにも難しいのだと痛感する日々です。
何がうまくいかなかったのか「盛り上がる店舗」になるためには検証したり、改善することが大事です。
私は経営者になってみて初めて、パンとは関係ない人間心理のことを勉強するようにもなりました。
仕事を辞める従業員の3つの理由
私も従業員で働く時代がありましたので、そこも含めてスタッフ側の視点でお話しをします。
従業員が辞めてしまう9割の原因は、浅い部分は人間関係だと感じています。
ですが、深い部分は「好きなことを仕事にできていない」「働く理由が腑に落ちてない」という本人の根本的な悩み、不安から、外的要因(人間関係や環境)を退社理由にしてしまうことが多いのだと感じています。
「やりたいことを仕事にしている」世界に解決しないトラブルはありません。
やりたいことをしてないから、不満が生まれ、トラブルは解決しないのです。
綺麗事かもしれませんが、この話は長くなりそうなので、また別の機会にでも語りたいと思います。
「やりたいことはあるけど、お金にならないからできない」という人もいるかもしれません。
やりたいことのために「お金を稼ぐ」という明確な理由があるのも、それもまた「働く理由」ですね。
何はともあれ「働く理由」があるから人は仕事をするのです。
働かなくていいなら、働かずに好きなことしてたいですよね。(笑)
例えば「お金を稼ぐ」という「働く理由」は、入社する前に給料額などで多くの人が働く前に知る最低限の情報を確認し、納得した上で入社していると思います。
従業員は、どうして退社していくのか?
それは何か特別な理由は別として、以下3つだと私は思います。
① 本人の「働く理由」が変わったか
② 健全に「働く理由」が実行できないと判断したか
③ 「働く理由」を忘れたか
もっと細かくしていくと複雑なパターンはあると思いますが、わかりやすいものだけ簡単にまとめてみました。
①は、本人からしたら快く応援して見送ってほしいですね。(笑)
②は、そう判断した「何か」が起こり、それに対して本人、会社ともに解決に真摯に取り組めたか?が大事です。
物理的に働く行為を妨害する行為や、精神的に妨害する行為(パワハラ・セクハラなど)、さまざまなケースがありますが、
一貫して「会社の良い機能が落ちている」ことに繋がっていますので、会社側は積極的に解決策を考える必要があります。
本人は勇気を出して、上司、上層部、オーナーに「不満、悩み」を相談することが大事ですし、会社側も気付けるように「不満・悩み」を言ってもらいやすい時間、空気、システムをつくるのも大事だと思います。
もし陰湿に他のスタッフをいじめたり、陰口、仕事を妨害したりするようなスタッフがいれば、それは③でしょう。
これは本人の問題でもあるし、「働く理由」を確認し続けていない会社側の問題でもあります。
何のために働いているのか、本人も訳がわからなくなっているかもしれません。
忘れてしまい、自分ではなく外的要因へ(他者・環境)へ無限に「不満」が広がっていきます。
その不満はエゴや幻で、その先に解決はありません。
今日の働く人たちは、疲れていて、余裕がなく、エネルギー不足です。
日々のストレスにより他人からエネルギーを奪おうとしてしまう人がでてきてしまうのも、仕方ないことかもしれません。
そこで「したいことを仕事にする」ことがいかに大事か、ということにも繋がってきます。
もし「パンを学びたい」という理由があり、学びたいけど給料が低いから辞めます、と言うパン屋スタッフがいたとします。
ここの判断は人それぞれですが、私の経験上「パンを学びたい」ことは、そこまで得たいことではないのではないか?
夢や目標が揺れているのではないか?と考えます。
本当に得たいことは、誰から妨害されても止められないのが人間性であることを知ってるからです。
答えは発する「言葉」ではなく本人の「行動」の中にしかないのです。
難しい話になってしまいましたが、ひとぱん工房は「働く理由」を応援する職場であり続けいたいです。
とある辞めていったスタッフの話
どんなに「働く理由」を確認し合い、関わっていても、中にはお互いにとってウィンウィンにならない人もいます。
とても真剣に、熱意を持って「パンを学びたい」という方が就職希望されたので、雇用しました。
オープン前のピークで、全員がバタバタと作業をしている中、その方は任された作業の手を止め、こちらの作業を見ていたので、私は「何ぼーっとしてるの!手が止まってる!」と怒りました。
その方は、私にそう言われたことでショックを受け、それを理由に辞めてしまいました。
とても傷ついて、ずっとそのことばかり考えてしまうので、働けそうにない。とのことでした。
確かに辞める数日前から、元気がなくなっていたので「何かありましたか?もしかして体調が悪いですか?」と、確認はしていましたが、「大丈夫です」と言う言葉に安心していました。
ここで時すでに遅し。
退職理由を聞いた時には、想像のはるか上を超えていたので唖然としましたが、すでに退職を決められていたので、一緒に解決する試みも何もできませんでした。
傷つけるつもりはありませんでしたと、謝罪の言葉を伝え、ただ仕事は真剣勝負なので、傷つけないように努力する約束はできても、二度と傷つけないという約束は無理です。と伝えました。
そして、その時点でパンを学びたい情熱はそこまで強くないと感じたので「パンを学ぶことを諦めるのですか?」と聞きました。
「それは諦めません、でもこれ以上傷つくのは無理なので。」と言われました。
私も何店舗かパン屋を経験しただけですが、優しく教えてくれる職場なんてなかなかありません。
なので、その人にはパン教室を勧めました。
でも、本人は納得いかないような顔をしていました。
収入を得ながらパンも学びたい。というところだったのだと私は思います。
なので、道は一つしかありません。
「優しく教えてくれるパン屋さんが見つかるといいですね、頑張ってください」と言ってお別れしました。
スーパーマン vs 個人店のパン屋さん
働いてみないとわからないことは多いです。
目的への情熱度合いも、飲食経営をしている人の教育の仕方も、お互いに分からないけれども、よろしくお願いします。なのです。
わかったつもり、変に期待することで、いらない不満を生むことになります。
なので私の経験上、従業員を雇う場合は使用期間を設けて、お互い大丈夫そうなら本採用する。という流れがお勧めです。
経営もできて、技術を教えることができて、人材マネージメントもできる。
スーパーマルチな人間で、尚且つ器が広く、仏のような精神で相手を信じ、人間性を見極め、いつでも愛で導ける人がいれば、不満もなく、やりがいを感じているスタッフがどんどん増え、必然的に店舗は盛り上がっていくお店になるということです。
さて、そんなスーパーマンは、この世界に何人いるのでしょうか?
大手パン屋は、そのようなスーパーマンを採用することは無理だと割り切り、ちゃんと役割分担ができていますし、不満を匿名で上層部に伝えるシステムにしています。
個人店では、それはかなり難しいことなので、仕方なくトップにあたる人間が全ての役を1人で担うことになりやすいです。
個人店のパン屋さんでは、「人がなかなか続かない」とよく聞きますが、私には当たり前だと思います。
難易度が高すぎるのです。
現在ひとぱん工房は「お店・スタッフが繋がって、お客様・地域が繋がっていく」満たされた感覚を、少しずつ体験しています。
マイペースですが、この素晴らしい循環を少しでも大きくできるように頑張っていきたいと思います。
ここまで読んでくださりありがとうございました。




について、どう思う?-1280x720-1.jpg)